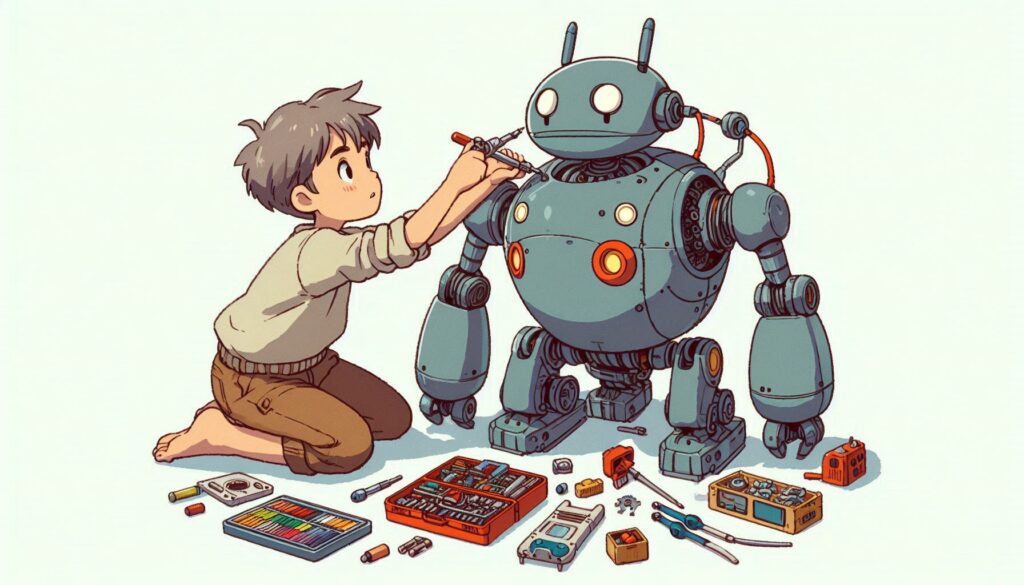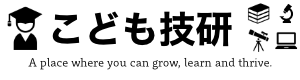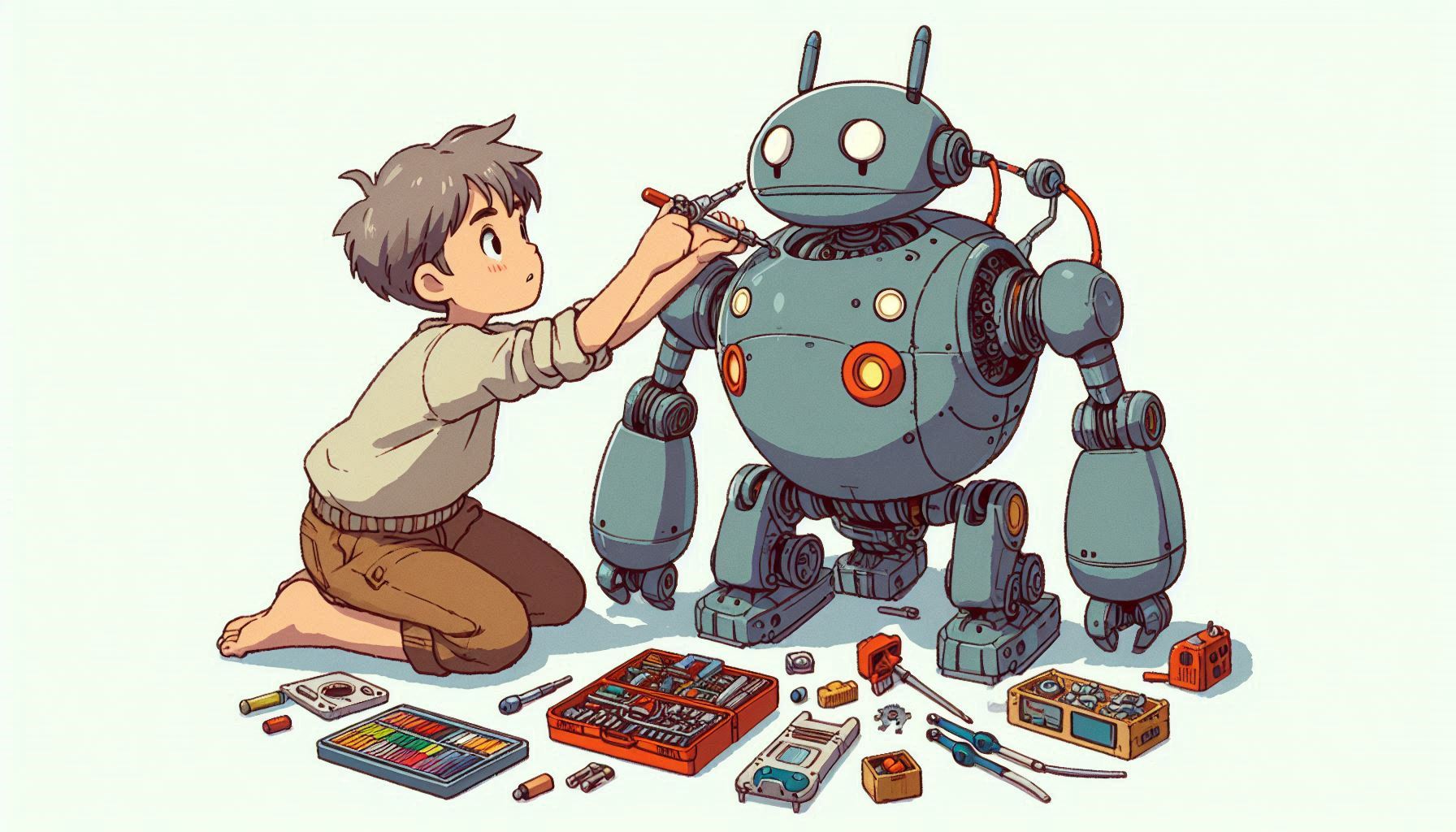40年ほど前の話です。
私は高校(正確には高専)の1年生から、公文式という塾で4年ほどアルバイトをしていました。
そこでは、こどもたちがプリントが終わったり、わからないところがあると、私のところへ来て言います。
「先生、教えてー」
「先生、採点してー」
アルバイトとして通い始めてすぐに、「これはやばい」と思いました。
こんな、まだ何も知らないちゃらんぽらんなガキが「先生」扱いされるのです。
もちろん、先生と呼ばれることで責任感が芽生えると言う考え方もあるでしょう。
けれどその後、私は進路に迷って、結局、学びの道を途中で折り返すことになるような子供でした。
立派な大人なんかじゃありませんでした。
幸いなことに、上品な奥様先生たちにまざって、ただ一人の男子でただ一人の10代でしたので、私のところへ来る子供たちは、やんちゃな子が多かったのです。
今の”ヤンチャ”じゃないですよ。昭和の頃の圧倒的ヤンチャです。半袖半ズボン、土まみれがデフォルトの元気の塊。
私は、元気が余りまくっているこうした子どもたちも本当に大好きでした。(*^^*)
ある日、その子たちに言いました。
「先生より、名前で呼んでーなー。安岡って」
「うん、わかった!」(ほとんどの子)
「おおっ‼️わかったわぁぁっー‼️」(←とある小学2年生。笑)
……のように、ちゃんと理解してもらえました。
こうして「先生」ではなく、
「安岡さん、採点して!」
とか──
プリントを『バーン!』と長机に叩きつけながら、
「わからへんのんじゃー💢💢💢 おっさーーんっっ!!」(←また別の小学2年生)
と、来てくれるようになりました。笑
わたしはまだ16歳くらいでしたが、”おっさん” で十分。笑
……老け顔でしたし!!笑
本当に、「先生」と呼ばれるよりも、ずっと居心地がよかったのです。(*^^*)
こんな体験から、私には、「先生」と呼ばれる関係性よりも、「ちょっと長生きしてる人」くらいとして相手をしてもらうのがちょうどいいのだとわかりました。
その後、大学生活でこどもたちの学習を見る機会のすべてで、「先生」ではなく名前で呼んでもらうようにしました。
「先生」と呼ばれないことは、私が調子にのらないと言うメリットだけでなく(笑)、わたしのことをこどもたちが身近に感じてくれると言う大きな気づきがありました。
これが、こども技研に“先生”がいない、いちばんの理由です。
保護者の方も、どうか「先生」と呼ばず、名前や「FINDER」とお呼びください。(*^^*)
よろしくお願いいたします。