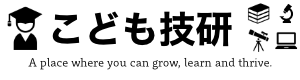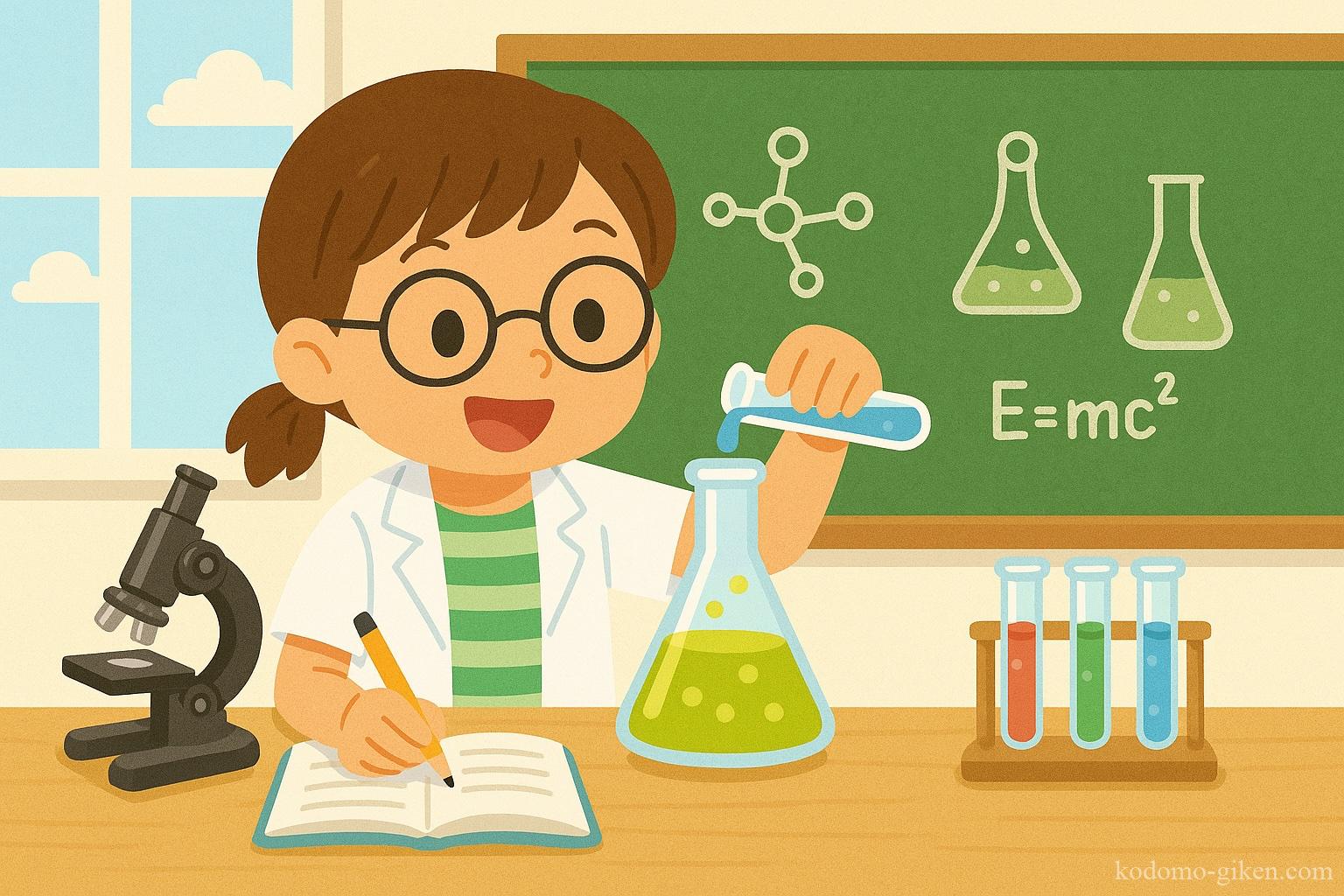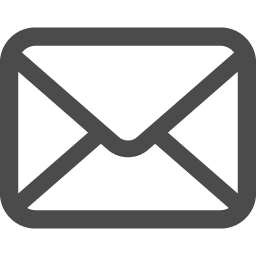こども技研では、学校の授業の各科目を、縦割りではなく、横にまたがってふれあい学びたいと考えています。
特に理科と算数。
本来数学は自然科学を理解するために作られた面があるから、理科とは切ってもきれない縁があるはずです。
世の中の広いことを「算数」「理科」等とジャンル分けして学ぶことは本来無理があって、授業の合理化や多数の生徒に対応するためになされている気がします。
こども技研は超少人数制なので合理化も平均化も気にしなくていいから、少しでも興味を持ちやすく、少しでも深入りしやすい道を、一人ひとりに合わせながら進みたいと思います。
学校の学びにも対応しながら、横にまたがる教科的学びをシステマティックに検討するため、以下のようなことをまとめたり考えたりしています。今回は理科で、ここから算数に繋いでいきますがそれは次回に。
| 学年\内容 | 植物・動物の観察 | 自然現象(光・音・力など) | 地学(天気・季節・地形など) | 水・空気・物質 | 実験・観察・記録スキル |
|---|---|---|---|---|---|
| 3年生 | 植物の成長と条件昆虫の育ちと体のつくり | 音の出る仕組み電気で明かりをつける | 太陽の動き風やゴムの力 | 水や空気の性質 | 基本的な記録・スケッチ |
| 4年生 | 季節と生き物(年に4回)命のつながり(メダカなど) | 光の性質電流のはたらき | 季節の天気の変化月や星の動き | 金属の性質水の温度変化 | 条件を変えた比較実験 |
| 5年生 | 植物の発芽・成長・結実魚の成長と観察 | てこのはたらき電磁石 | 天気の変化と雲の動き | 水溶液と溶け方ものの変化 | 詳細な観察・測定 |
| 6年生 | 生物のからだのつくりと働き人と動物のくらし | 水の力・てこの応用電気の利用 | 地層・火山・地震太陽と地球 | 燃焼の仕組み物の体積・質量 | 実験結果の整理と考察 |
| カテゴリ名 | 内容の例 |
|---|---|
| 植物・動物の観察 | 成長、構造、生態、季節との関わり、生物同士の関係など |
| 自然現象 | 光、音、電気、力などの物理的な現象の理解 |
| 地学(天気・季節など) | 気温や天候、天体、地面のようす、自然環境の観察 |
| 水・空気・物質 | 状態変化、水溶液、燃焼、質量などの化学的な性質の理解 |
| 実験・観察スキル | 科学的な思考力や方法、記録・比較・分析などのスキル面 |
さらに中学校以降の分類でまとめ直すと!
| 学年\分野 | 物理(光・音・電気・力など) | 化学(水・空気・物質・変化) | 地学(天気・天体・地形など) | 生物(植物・動物・からだ) |
|---|---|---|---|---|
| 3年生 | 音の出る仕組み電気で明かりをつける風やゴムの力 | 水や空気の性質 | 太陽の動き(方角と影) | 植物の育ち方(条件と成長)昆虫の育ち方と観察 |
| 4年生 | 光の反射電流のはたらき | 水のあたたまり方金属の性質 | 季節の天気と気温の変化月と星の動き | 季節と生き物(四季の観察)命のつながり(メダカなど) |
| 5年生 | てこのはたらき電磁石の仕組み | 水溶液とものの溶け方ものの燃え方(導入) | 雲の動きと天気の変化 | 種子の発芽・成長・実のなり方魚の育ちと観察 |
| 6年生 | 水の力のはたらき(流れ・浮力)電気の利用(発電・モーター)てこの応用 | 燃焼の仕組み物の体積と質量の変化 | 地層・火山・地震太陽と地球の関係 | 人のからだのつくりと働き動物の生活と環境 |
補足ポイント
- 物理分野では、「光・音・電気・力」の基本現象を体験を通して学ぶ。特に「てこ」「電気」は5〜6年で本格化。
- 化学分野では、「水や空気の性質」から始まり、「水溶液」や「燃焼」「質量の保存」などの導入を扱う。
- 地学分野では、「天気」「月と星」「地層・火山・地震」などを中心に、観察と記録が重視される。
- 生物分野は毎学年で扱われ、植物や動物の成長、季節との関わり、命のつながり、人の体のつくりまで幅広く学ぶ。
小学校ではこんなに広く理科を学んでいます。しかも実験や観察は割と人気の授業だったはず。
なのに中学、高校と進むにつれて科学に興味をもつ子供が減っていくのはなぜなんだろう?
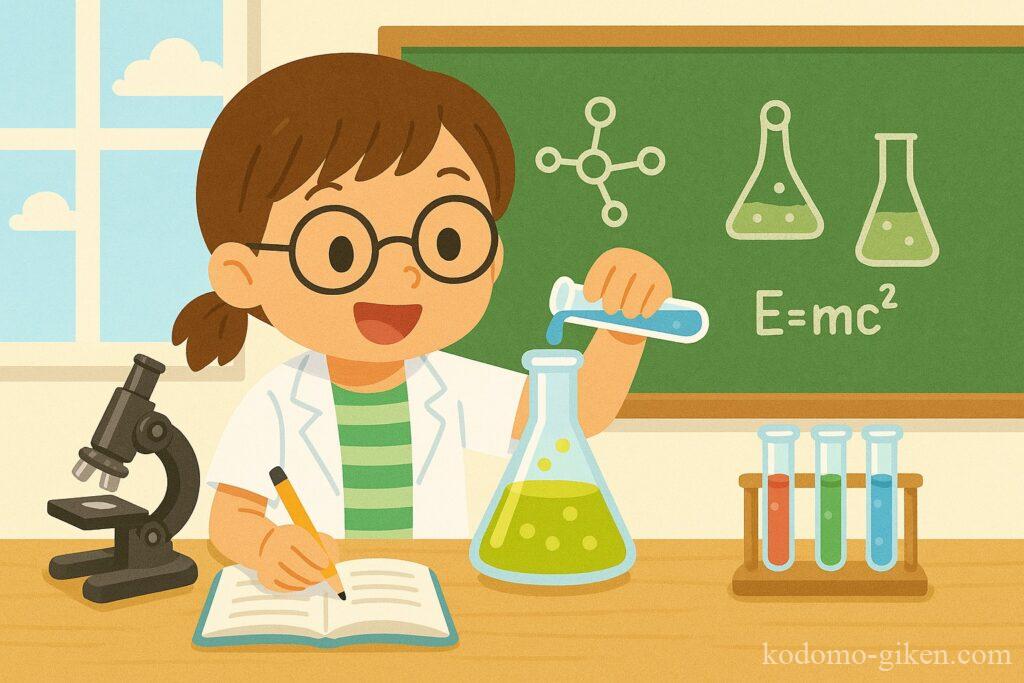
次回は小学校での算数を整理します。