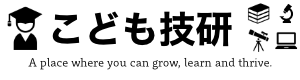なぜ、こども技研では小学生にスマホを持たせていないのか?
最近では、小学生でもスマートフォンを持っているのが当たり前になってきました。
だけど、こども技研では「小学生研究員がスマホを所有すること」を禁止しています。
それは、スマホが悪いからではありません。
スマホがこどもたちから奪うもの
こども技研が心配しているのは、こどもたちの“器”が、知らないうちにスマホの情報で埋められてしまうことです。
スマホには楽しいものがたくさん詰まっています。便利な道具でもあります。
でも、そこにあるのは とても強くて、絶え間ない刺激です。しかも見ているこどもの好みを知って、もっともっと見させようとします。
動画、ゲーム、SNS、通知…。毎日のように届くそれらの情報は、こどもたちが本当に感じたり考えたりするはずだった時間や余白を、少しずつ削ってしまいます。
では、その「器」には、いったい何が入るべきなのでしょうか?
こども技研が大切にしているのは、たとえばこんなものです:
- 自分の中から湧いてくる問いや好奇心
- 時間を忘れるような集中と没頭の体験
- 頭の中で物語をつくる想像力や空想する時間
- 感情を感じて、整理する力
- 目の前の人とのやりとりから学ぶ関係性の感覚
こうしたものは、大人が教えたり渡したりするものではありません。
こどもたちが、その「器の余白」に、自然と大切なものを入れていくものだと思います。
スマホを持つ代わりに
こども技研では、まず「やってみること」「考えること」「つくること」を大切にしています。
スマホがなくても、パソコンやカメラを使って、自分で工夫したり試したりすることはできます。
スマホを触ることは、全然難しいことではありません。
LINEやSNSも、必要なときが来れば、子どもたちはすぐに覚えるでしょう。
そんなに急ぐことはありません。
映像やデジタルの力はとても魅力的ですが、それを“見続ける”だけでは、本当の体験にはつながりません。
受動的な体験は、能動的な体験とは全く別物なのです。
アニメ映画監督の宮崎駿さんも、こんな言葉を残しています:
「トトロの映画を1回見ただけだったら、ドングリでも拾いに行きたくなるけど、ずっと見続けたらドングリ拾いに行かないですよ。なんで、そこがわからないんだろうと思うんだけど。」
引用:虫眼とアニ眼 – 新潮文庫
宮崎 駿 Hayao Miyazaki
アニメ監督 1941〜
やってみたいと思ったとき、すぐそばにある自然や好奇心に、ちゃんと「自分の手」を伸ばしてほしいのです。
画面の向こうではなく、自分の目と手と心で、世界と出会ってほしいのです。
大人になってしまうと感じることができない、こどもの頃にしか感じられないものがあります。
それは、成長とともに遠ざかっていく、かけがえのない時間です。
こども技研は、こどもたちにそんな時間を大切にしてほしいと願っています。
スマホを禁止することには賛否あると思いますが、こども技研はこのように考えています。