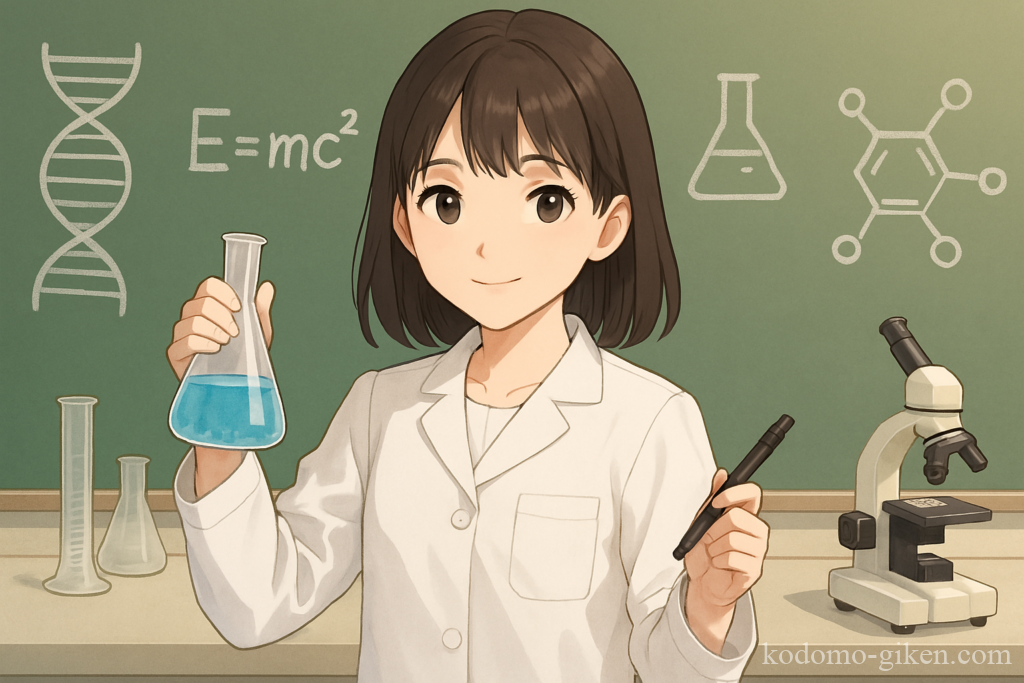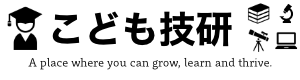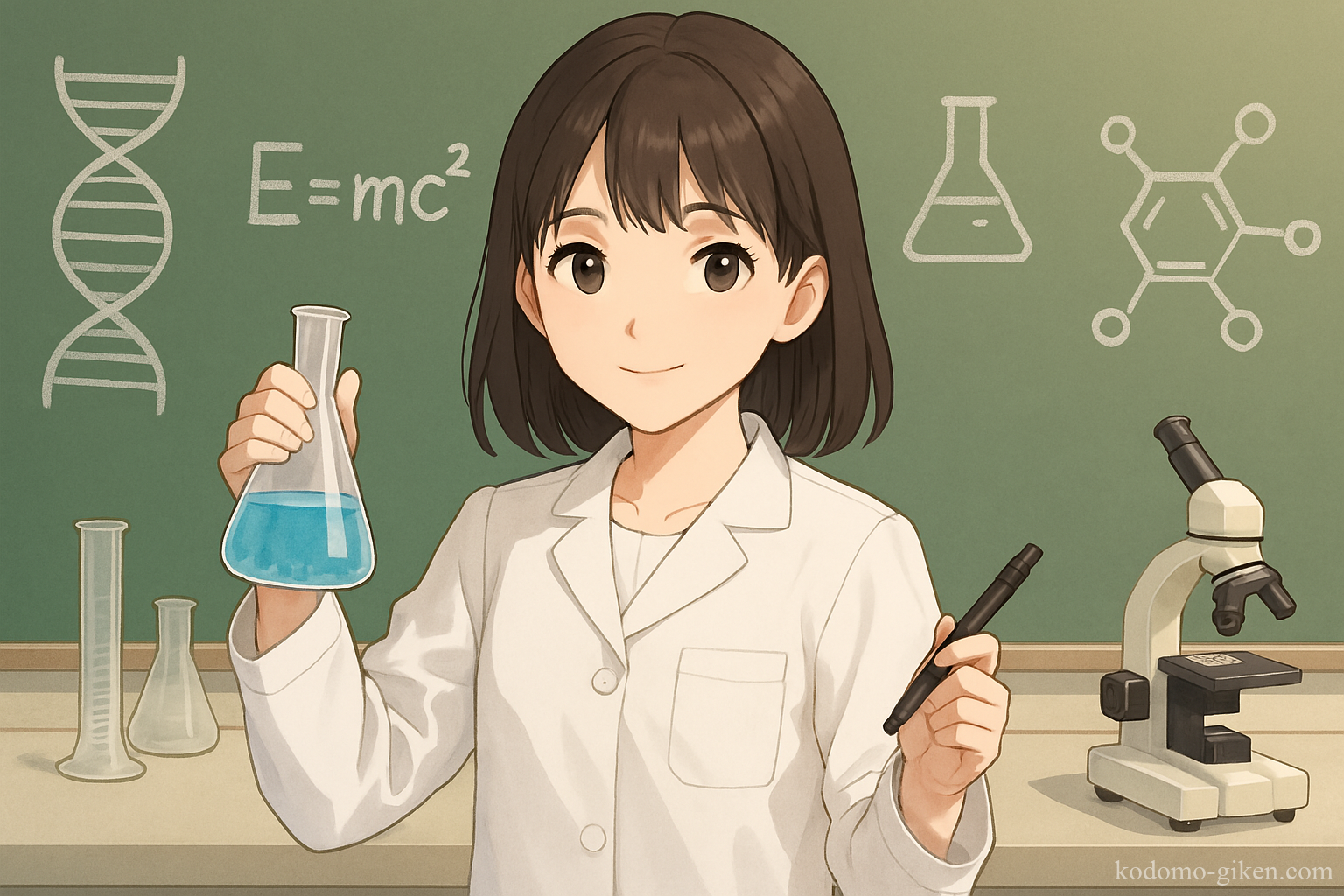はじめに
海外の自然や科学、技術関係のドキュメンタリーや映画を見ていると、女性の研究者やエンジニアが当たり前のように登場します。
彼女たちが自分の専門分野を語る時、とてもいい目、いい表情をしています。
「どう?こんなに素敵なのよ。素晴らしいでしょう。私はこの分野に進めて幸せなの」
男性研究者・エンジニアが語るときもそうなのですが、みなこのような雰囲気で熱く語ってくれます。
ではなぜ海外では、女性が自然に理系の道を歩んでいるのでしょうか。
最近、日本では、理系分野に進む女性を増やそうと、大学の理系学部に女子枠が作られるようになってきました。
でも私は、その前にもっと大事なことがあるのではないかと思っています。
原点は「やってみたい」という体験
ドキュメンタリーで見る研究や技術の道に進んだ女性たちは、10代の頃までに「やってみたい!」と思える体験をしています。
それは学校や家庭、科学的な施設やイベントでの体験です。
体験がなければ、その道に進もうとは思わない。
これはとてもシンプルな事実です。
では、なぜ日本ではその体験が少ないのか?
理由はいくつか考えられます。
- 科学が暮らしから遠い
- 科学が「勉強」「テスト」の道具になってしまっている
- 科学に触れる機会が限られている
でも、もっと大きいのは「文化」の違いではないかと考えています。
海外では科学が暮らしに根付いている
アメリカやヨーロッパの家庭では、科学は勉強ではなく、遊びであり、生活の一部なのではないでしょうか。
• 科学博物館やサイエンスセンターが街に多い(例、日本:約100館、アメリカ:約440館 2021年データ)
• ガレージ文化・DIY等の手作りの文化が根付いている
• 複数の科学番組専門チャンネルが日常にある(日本では子供向けに一部科学番組が存在するのみ)
• 親子で修理や実験をする時間が当たり前
このように欧米では、暮らしの中に「考える」「試す」「作る」「直す」が自然にあるのではないかと考えます。
子どもを一人の人間として尊重する文化
もうひとつ大きな違いがあります。
海外(特にアメリカ)では、子どもが親に意見を言い、大人がそれを受け止める姿が当たり前にあります。
映画やドラマでもよく見るシーンです。
一方日本では、大人が子どもにマウントを取るような態度がまだまだ珍しくありません。
学校の教師ですら、導くというよりも支配しようとする態度を取る人がいます。
日本では「子どもは未熟だから大人が教え導くもの」という前提。
けれど、科学に限らず、何かを「やってみたい」と思える感性は、普段から「考えていい」「意見を言っていい」「試していい」「失敗していい」という環境の中で育つものではないでしょうか。
同じ体験をしても、心に残る人と残らない人がいる理由
大事なのは、体験の数だけではありません。
同じ体験をしても、それを心に残すかどうかは、その人がそれまでにどんな時間を過ごしてきたかによって違ってくるのではないでしょうか。
例えば、濃い味の食べ物ばかりを食べ続けるように、刺激の強い娯楽を日常から感受していたら、自然科学のような薄味の、集中して初めて興味が持てるようなものには、心が動かなくなるのではないでしょうか。
このような感性は、日々の生活の中で、身の回りの大人の感性の影響を受けながら成長していく気がします。
だからこそ、女子枠の前に必要なことがある
女子枠を作ることは、「女子枠を作った学校の理系女子学生を増やすこと」には意味があるかもしれません。
だけどそれは、所詮、大学同士での学生の奪い合いにすぎません。
「女子枠?だったら私、理系に行くー!」なんて文系から変える高校生はいません。
だからもっと大きく「理系をめざす生徒を増やす、理系を楽しいと考える生徒を増やす」と考えて、小さい頃から「やってみたいと思える体験」や、それを受け止められる感性を育てる環境の方が、もっと大事なのではないでしょうか。
それがあれば、特別な枠を作らなくても、理系に進む女子(もちろん男子も!)は自然に増えていくのではないでしょうか。
私はそう考えています。
おわりに
日本は資源がない国だから、昭和の時代は皆が同じように足並みをそろえて協力して、他の個々バラバラの国ではできないことをしてきました。だから強すぎる個性よりも協調性、悪い言い方をすると同調性が重視されてきました。
けれど『自分をあまり出さずに周りに合わせて身を預ければ一生安泰』、そんな時代は終わってしまいました。
企業は社員ではなく株主のものという考えが増え、短期的な利益を求める方向性が強くなりました。そうなると従業員は「会社の財産」ではなく「コストの原因」と見做されてもしまいます。
企業に一生は頼れない時代、普通の子供が人生を普通に生きるためには、それぞれが自分の強みをしっかり知って、その部分を強くしならなければならないでしょう。
簡単ではありませんが、「機会と環境を作る」という基本的で地味で長い道のりが、科学が好きな子供が、自分の得意なジャンルを活かすべく、理系に進む方法ではないでしょうか。
私たち科学関係の道を進んでいる大人は、科学が好きな(or 好きになるかもしれない)子供のために、科学の道に進みやすく、より遠くへ行けるような環境を作らなければいけないと考えています。