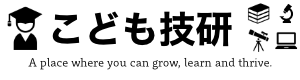写真を撮ってみたら、「なんか黄色い…?」「青っぽくなってる?」
そんなこと、感じたことはありませんか?
それは「ホワイトバランス(WB)」と呼ばれる仕組みが関係しています。
今回は、カメラが「光の色」をどう見て、どう写しているのかを、やさしく見ていきましょう!
光には“色”がある?
わたしたちの目には、光の色はあまり気にならないかもしれません。
でも、実は「晴れた日の光」と「電球の光」とでは、光そのものの色がぜんぜんちがうんです!
たとえば、白い紙を太陽の下で見ると白く見えますし、部屋の中で電球の下で見ても白く見えますよね?
これは、目や脳が自動で補正してくれているからです。
当たっている光の色が違うから本当は違う色になっているのに、「同じ色だ」と脳で補正されるのです。
でも、カメラはそう簡単にはいきません。
「白」という色は、現実の世界ではとてもたくさんの種類の白があります。
よーく見ると黄色っぽかったり、青っぽかったり、グレーっぽかったり。
その差をひっくるめて、「白」と思うのは目と脳の仕業です。
写真の仕事の世界では、「標準の白」や「標準のグレー」を使って、差がないようにしていきます。
ホワイトバランスってなに?
カメラが「どの光を“白”とみなすか」を設定するのが「ホワイトバランス(WB)」です。
晴れの日の青っぽい光、電球のオレンジっぽい光、蛍光灯の緑っぽい光──それぞれに合ったWBを使わないと、写真全体の色がかわってしまいます。
色温度(ケルビン)って?
光の色を数字で表すとき、「ケルビン(K)」という単位を使います。
| 光の種類 | 色温度(目安) | 見え方 |
|---|---|---|
| ロウソクの光 | 2000K〜3000K | 赤っぽい |
| 電球の光 | 3000K〜4000K | オレンジ |
| 太陽の光(昼) | 5000K〜6000K | 自然な白 |
| 曇り空や日陰 | 7000K〜8000K | 青っぽい |
数字が大きいほど青っぽく、小さいほど赤っぽい光になります。
オートWBとプリセットWB
最近のカメラやスマホには「オートWB(自動補正)」が入っています。
これは、写った写真のデータを見て、カメラ自身が「このデータだとこの色温度がいいよね」と自動でWBをセットしてくれる機能です。
でも、光の色によってはうまく補正できないこともあります。
そんなときは「プリセットWB」を使ってみましょう!
- 晴れ(Daylight)
- 曇り(Cloudy)
- 日陰(Shade)
- 電球(Incandescent)
- 蛍光灯(Fluorescent)
- カスタム(マニュアル設定)
WBを変えるだけで、同じ場所・同じ被写体がまるで違って見えるので、ちょっと試してみるのも楽しいですよ。
窓からの日光と屋内の照明など、同時に2種類以上の光源があるシーンは、オートWBが苦手な状況です。このシーンだと屋内がメインの被写体だと思いますので、手動でWBを設定したり、フラッシュを光らせたりしましょう。(フラッシュの光は強いので他の光の影響を少なくします。カメラはフラッシュを使った時点で、フラッシュ中心のオートWBになります)
やってみよう!
スマホのカメラでも、設定を変えられる機種があります。
同じ部屋で「WBを変えて撮る」だけで、全然ちがった写真になります。
「正しい色」だけじゃなくて、「どう見せたいか」を考えるきっかけにもなりますよ😊
WBを変えると写真が全然変わってきます。(スマホのフィルターもWBを触ったりしています)
人の感覚が色に敏感なものは、「人の肌の色」や「白」です。オートWBで違和感があれば積極的にさわってみてください。
まとめ:色は光で決まる!
写真は、「立体的な空間の光を2次元に投影するもの」です。
だから、写真に写る“色”は、光の色にとっても左右されます。
ホワイトバランスを知ると、「あれ?なんかちがう…」という写真が、ちゃんと“思った色”で写せるようになります。
少し前の投稿の「【こども技研web写真教室】画像ファイルってなにがちがうの?RAWとJPEGとビット数のひみつ」でふれた「RAWファイル」は、後からWBを変えることができます。
機会があればRAWで撮って、WBを変えてみてください。
カメラの中では、「RAWのデータをみてWBを決めてJPGに書き出す」という作業をしています。
だからRAWデータがあれば、後からWBを自由に変更できるのです