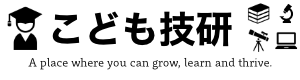はじめに
学校の生活科や理科の時間は、実際に身の回りのことから経験することが多いので、わくわくすることがたくさんあります。
そんな体験の中で「もっと知りたい」「もっとやってみたい」という気持ちが生まれることがあると思います。
その先に進もうとすると必要になることが多いのが算数です。
植物の観察をしたら「大きさ」を比べたくなったり、地図を描いたら「距離」や「広さ」を知りたくなったり、自分のやりたいことのために、算数が必要になる場面が出てくることがあるでしょう。
「言葉は最初に身につけるべき道具」とこども技研ではよく書いていますが、数字もそれと同じように、最初に使えるようになるべき道具です。
なぜ、教科をつなげたいのか
学校では、教科ごとに時間がわかれています。
理科は理科の時間、算数は算数の時間。
でも、こどもが出会う世界はそんなふうに分かれていません。
生活の中で出会う「ふしぎ」や「知りたいこと」は、いつでも全部がつながっています。
たとえば、外で虫を見つけたとき、「どこにすんでいるのかな?」と考えるのは生活科や理科の学びです。
「何びきいるのかな?」「体の長さはどれくらいかな?」と考えると、理科の学びに加えて算数の学びも入ってきます。
「卵はどのくらい産むのかな?」「大人になれるのはどのくらいかな?」、こうなると数学の世界に踏み込み始めます。
世界を知りたいと思ったとき、算数はとても便利な道具になります。
これは当然です。
数学は目の前の世界の真理を見つけるために生まれてきたのだから、現実の世界を体験している先に算数があるのです。
だから思います。ひっつけてしまえばいいやん!
こども技研での学び方
こども技研では、まずこどもたちが「やってみたい」と思う体験を大切にします。
身の回りのものを観察したり、実験をしたり、外に出て調べたり、そこで出てくる「これって、どうなっているんだろう?」という気づきが、学びのスタートです。
そこから、「はかってみよう」「くらべてみよう」「まとめてみよう」と思ったときに、自然と算数が出番になります。そのタイミングを逃さないようにサポートします。
算数が「やらされるもの」ではなく、「自分のやりたいこと、知りたいことを実現するための道具」になってほしいと考えているのです。
これからの学びのカタチ
私がこどもの頃は、お父さんは日曜日以外仕事、平日の僕たちは学校へ行って、帰ってきたらテレビを見て、というみんな同じような体験をしていました。
だけど、今はネットの時代、多様性の時代です。お父さんお母さんたちの休日も増えました。だからこどもであっても、それぞれが日常から異なる体験をしています。
そんな時代だから、教科で学びを切り分けるのではなく、個々の体験や探究の流れの中に自然に算数や他の学びが出てくる。そんな学びのスタイルが合っているのではと感じています。
体験は個々で違うので入り口が違うことになりますが、その先にある算数や数学は同じです。ゴールは同じになると思います。
学校のカリキュラムはとてもよく考えられていて、いろんな学びが絡み合いながらステップになっています。
その最初のステップをいろんなところから始められるといいね、という考え方です。
この方法では一人一人が異なる地点からスタートをすることになります。
人数や時間の制約がある学校では難しいと思います。
でも、こども技研は小さな場所です。だからできることがあります。
こどもたちの「やってみたい!」を出発点にして、学びをひろげ、深めていきたい。
楽しい体験の中から、さらに先へ自分で学びを進めたくなる。
「好奇心が学びの扉を開き、楽しさに気付いたこどもたちがそこから先を歩いていく」
そんなに簡単なことではないとわかっていますが、そんな形がこども技研が考える理想の『これからの学びのカタチ』です。