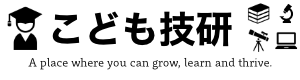こども技研では「失敗から学ぶ」という方法を大事にしています。
ただし、これは一見シンプルなようで、実は他の習い事ではなかなか成立しにくい方法です。なぜなら、保護者の方の理解があってはじめて成り立つからです。
習い事風アトラクションの限界
最近は「習い事風アトラクション」とでも呼ぶべき教室が増えています。
ブロック教材や人気ゲームのみを題材にして“楽しい”を前面に出すスタイルです。子どもたちはワイワイと遊び感覚で参加できるし、親も「うちの子はプログラミングをしている」と安心できます。
でも、よく見ると“本当の失敗”が用意されていないように見えます。
こうした方法は、テキストや動画に沿って進めれば、必ず成功できる課題、盛り上がる演出、達成感で終わる仕組みになっています。
子どもたちの作業は時間内に完了し、全員の足並みが揃います。
完了しないようだったらスタッフが介入するからです。
だから全員が同じように達成感を味わうことができます。
この手法での分かりやすい価値ですが、子どもが「うまくいかない自分と向き合う」場面はほとんどありません。
こうした「習い事風アトラクション」でも「失敗から学びます」とよく唄われますが、ここでいう”失敗”とは、安全に演出された“つまずき”にすぎないように感じてしまいます。
楽しさはもちろん大切です。
だけど “必ず成功する道” しかないと、子どもは「挑戦してみる」、「うまくいかない自分と向き合う」経験を失ってしまいます。
子どもたちがゲームを好きなのは、少ない努力で必ず成功できるから。危なくなればリセットできるからです。
でも、現実の学びの場でそれを繰り返してしまえば、失敗から立ち上がる力は育たず、社会に出た瞬間に挫折するケースが起きます。
「習い事風アトラクション」は、今の楽しさだけを見ていて、子どもたちの将来に必要な力を見ていないように思えるのです。
こども技研のスタイル
こども技研では、普通のプログラミング教室が「失敗から学ぶ」と言っているレベルのことは、前もってフォローすることがあります。
なぜなら、それは大人になって同じことをしても、ただ直せば済むミス程度で、失敗と言うほどのことでないからです。
だけど、普通のプログラミング教室が「絶対放置しないこと」をこども技研は放置します。
そして大きな失敗をしてもらいます。「うわーやっちゃった!🥲 先生にはいえない!😭(こども技研には先生はいませんが)」レベルの失敗です。
このくらいの失敗をして初めて「心に残る」のではないでしょうか?
ちょっとした見逃し、ケアレスミス程度の、心に残らないものでは失敗とはいえません。
こんなすぐわかるようなことを、他社さんがしないのはなぜか?
ひとつは、教室運営の効率化のために、こどもたち全員を同じスケジュールで進めるからです。
それに、指導する人がプログラムを業務で作った経験がないので、マニュアルから外れると指導できないからです。
そして、「今日は進みませんでした」と保護者の方へ言えないからです。
こども技研がそれをできるのは、
- 業務(先輩からの教育、後輩の育成)での経験から、この行為は正しいと確信していること。
- 保護者の方へ説明する覚悟があること。
- そして保護者の方が『きっと理解してくださる』と信じていること。
――この3つがあるからです。
こども技研は、保護者の方の大きなご理解のもとに、子どもたちに自分のペースで進めることができる、のびのびとした時間を提供させていただいています。
フォローしないからこそ生まれる問い
例えば小さな研究員が、「もう一度最初から作り直さないといけないような失敗」をしてしまった時、「失敗は仕方ないよ」とフォローします。
失敗はそのまま受け止めてもらいますが、心は必ずフォローします。
そして、時に様子によっては、「嫌になったの?」と聞きます。
すると、そのレベルになっているとほぼ確実に「もうやめたい」と言います。(気持ちをそのまま言ってもらえる環境作りが大切だと思います)
大人が先読みしてフォローして“成功風”にまとめてしまったら、出てこなかったはずの言葉です。
普通の教室なら「取り返すのが大変な失敗」をしそうな時はすぐにアドバイスします。
「そこ、あってる?」とか「まちがってない?」とかの言葉です。
私ももちろん言いたいです。大人の目だと失敗が目に見えているんですから。
だけど、言っちゃだめなんです。失敗してもらわないと。
こども技研では、そのまま失敗してもらって、心が折れてたら、「じゃあやめて何しようか?^^」と次へ進みます。
重い失敗もそのまま受け止めてもらいますが、まだこどもなので、心のフォローは必ず行います。
「習い事風アトラクション」が「軽い失敗を軽く回復させて」、「楽しかった!」で完結するのに対して、こども技研は「じゃあやめて何しようか?^^」で終わります。
これは全く別の体験です。
ここでも「信頼している」ことが生きてきます。
次の回の時、心の充電を済ませた子どもたちは、自分からこう言ってくれています。
「あの続きする!」と。

まとめ
「失敗から学ぶ」という方法は、教育的に聞こえはいいけれど、実際に運営しようとすると難しいものです。
大きな失敗をしてもらおうとすると、みんなが同じペースで進める講座は成立しません、あらかじめ答えを見せているテキストや動画で進める授業でも成立しません。
また、大きな失敗をしてもらえばもらうほど、信頼関係と、フォローする側にカバーできるスキルが必要になります。
こども技研で「失敗をしてもらう環境」ができているのは、保護者の方が一緒に「学びを育ててくださっている」からであることは間違いありません。
これからも、ここにしかない学びの場を作っていきます。
理系の道を進む子どもたちは、やがて社会に出て、技術者や研究者の仕事に就くことが多いと思います。
その時に必ず求められるのは「責任感」です。
今はまだ小さな子どもたちでも、将来は人の安全を守ったり、ときには命そのものに関わる仕事をするかもしれません。
しかし、その時には「やり直し」や「リセット」ができません。
だから、「プログラミング教室」といった職業の入り口を体験するような学びを扱う場では、子どもたちに覚悟の根っこになる部分を伝えることが大切だと考えています。
職業に夢を見させる教室は、大人の都合のために、大切な失敗をする機会を奪ったり、あらかじめ設計された単純な達成感を与えてはいけないと思います。
子どものうちに「もういやだ!」と思うくらいの失敗をたくさん経験して、大人になってから「してはいけない失敗」をしないでほしい。
それが、失敗の恐怖に命を縮めながら現場を歩んできた、一人のエンジニアとしての強い願いです。