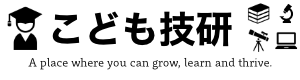AI の時代になって、成果物だけで子供を評価する教育は限界を迎えます。
必要なのは、こどもたちに「考えるプロセス」を経験してもらうこと、それを見守ることができる体制を整えることではないでしょうか?
■ 結果主義の教育が抱えてきた課題
学校や塾では長いあいだ、点数や仕上がりの良さという「結果・成果」が子どもの評価軸になってきました。
それは「時間がない」、「人手不足」等の理由です。
「結果をみる教育」は、「測りやすさや公平性」を考えればバランスの取れた方法でした。
だけどこの方法は、学びの中でいちばん大切な「どのように考えたか」という部分を置き去りにしてきました。
どんな思考をたどったのか、どれだけ深く悩んだのか、どこでつまずいてどう乗り越えたのか。本来そこに学びの価値があるのに、成果物だけが評価される仕組みでは、子どもたちの努力の軌跡は見えなくなっていきます。
現代の学校では昭和・平成の時代とは異なり、「授業への積極性」や「態度」などのプロセスを評価する項目も扱われています。
しかし現実を知っている保護者には、「理解しているから質問しないと“積極性がない”と見なされる」、「同じ態度でも先生によって評価が変わる」、「先生との相性で評価が揺れる」などの場合があることは、体験として理解されています。
■ AIが登場した瞬間、この弱点が一気に表面化した
ChatGPTのようなAIは、文章を短時間で整えてしまいます。構成や文体がきれいで、見た目のクオリティもとても高くなります。すると結果だけを見る教育では、「努力するよりAIの方が早くて上手い」という誤った価値観が生まれます。
ネットの掲示板には、大学生の「自分で苦労してレポートを書くより、AIに書かせた方がいいものができる」という声すらあります。これは努力を否定したいわけではなくて、結果主義とAIの相性が悪すぎるために起きている現象です。
結果だけを評価基準にしてしまうと、子どもたちは「考える価値」を見失ってしまいます。
このままでは、努力を軽視する文化が生まれるのも当然の流れのように感じます。
■ 本当に育てるべき力は「問い」と「プロセス」
AIは文章を整えるのは得意でも、物事を深く理解したり、矛盾に気づいたり、自分の意見として再構築したりすることはできません。
ですが、まだ発展途上中の青年たちは、AIのその点に気がつくほど実力が伴っていない場合が多くあります。
そうすると、上記のように「AIがあるから努力がむなしい」ことになるのです。
そうじゃないのです。
「世の中のことを調べてまとめて文章にする」なんて、AIが最も得意とするところです。
人がやらなければならないのは、「その件を頼んだ理由」と「その情報をどうするか」。つまり、「それまで」と「そこから」なんです。
それに、AIがまとめてくれたその文章も、嘘であることが多々あります。
しかし、それが嘘であること見抜くには、その分野の知識と経験が必要です。学生さんにはまだないことも当然あります。
若い人たちは、AIを使いこなせるように、そのための「経験」と「実力」を養って欲しいのです。
つまりは「考えよう!」ということです。
「疑問に思い」、「その疑問を考える」、「行動する」、「結果に責任を取る」。
この経験の積み重ねが、実力を養い、自信をつけます。
■ プロセスを見守る教育は、AIを“危険”ではなく“味方”にする
その若者が「考える経験を積むことができる環境」を、大人は整え、見守る必要があるのではないでしょうか。
「考える」ことを真剣に始めると、AIはズルの近道ではなく、自分が考えるための道具・秘書になります。
すでに、AIを利用するその道のプロは、そうした用途で使っているはずです。
例えば、
- 自分で考えた内容を文章化する手伝いをしてもらう。
- もっと多角的な視点が欲しい時にサンプルをもらう。
- 調べる範囲を広げるサポートを受ける。
こんなふうに、AIを“考える人を支える側”に置くべきなのです。
そして、そうできるのは、プロセスに価値をおく教育だけです。
AIに奪われる学びではなく、AIを使って深める学びに変えなければなりません。
■ 結果主義からプロセス主義へ。教育は原点に戻る時期に来ている
効率や公平性を優先したこれまでの教育は、結果主義に偏ることが多くありました。
でもAIが登場した今、その仕組みは見直しが必要になっています。
大人の側は、従来の形を大きく変える必要があると感じます。
子どもたちの学びは、点数でもレポートの出来でもなく、その途中にある「考えた時間」そのものに価値があります。
しかし、その「考えた時間」を見守るには、1対多数では難しく、一人一人にしっかり寄り添う「大人にとっては時間・費用・人的に効率が悪い」方法しかありません。
それでも、子どもが本当に成長していくという視点で見ると、その“非効率な方法”が「子どもの成長という点」においては、むしろ最も効率が良い学び方ではないでしょうか。
この方法は、小中高校の一般授業では難しいですが、部活動などの少人数の時間や、大学での研究室・ゼミの期間などでは行われていると思います。
学校の先生は熱心な方がおられると思います。その方々がしっかりと子どもたちひとりひとりを見守ることができる、プロセスを大切にできる環境をつくっていくべきではと、子を持つ一人の親として、そう考えています。
AIが進んでも、考える力は自分の中でしか育ちません。
その時間をどう積み重ねるかが、これからの学びを決めていくと思います。
この時間を守れるかどうかが、これからの教育にとって大切な鍵になるように感じています。