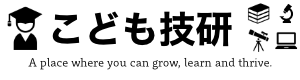今日はかなり難しい製作のお話です。
ですがその前に、前回紹介できなかった、ちょっと難しい製作編の完成形を紹介します。


作ったのはタミヤのスケートロボットでした。^^
大人なら全然難しくないものですが、小学校低学年には難しかったと思います。
要点は、
- 図面を理解すること
- ドライバー等の工具の使い方を覚えること
- 電気の配線に触れてみること
こういったことでした。
スターターの段階をクリアできたので、今回から難しい製作に入ります。
一気に難易度が上がるので、大人のアシストも増えますが、この製作での一番大切なことは「失敗してもあきらめずに続けることに慣れる」ことです。
さらにものづくりの基本として学んでほしいことは、
- 段取りをする
- 部品を丁寧に扱う
- 一つ一つの作業を確実に行う
と言ったことです。

ですが、まだ小さいのでどうしても色々と失敗します。これは仕方がないことです。^^
失敗の理由は「経験値が少ないこと」と「ワクワクしすぎて気が急いてしまったから」がほとんどです。
とてもかわいい失敗です。(*^^*)
具体的にはこんな失敗です。大人のみなさんも通ってきた道だと思います。
- 次のことよりももっと先のことが気になって、作業がおろそかになってしまう
- 気になるから、部品を色々出しすぎて無くしてしまう
- 作業ごとに整理をしないから、部品を見つけられなくなってしまう
こうした点は少しずつアドバイスします。
- 次に使う部品だけトレーに出そう
- 使わないものは片付けよう
- 図面をしっかり読もう
と言ったことです。
こちらは作業中の光景です。
図面の細かさから、かなり難しい製作であることがお分かりいただけると思います。

右の黒いものはノギスです。
部品点数が多いので、整理用のボックスを手渡すと、パーツの用途別に、とても上手に整理してくれました。^^

こども技研では、毎回最後はレポートを書きます。
レポートといっても難しいものではなく、「今日やったこと」、「どう思ったか」を書くだけです。
レポートを書くことによって、「行動や環境を言語化すること」に慣れてもらえればと思っています。
学校のテストでも、「国語は成績を伸ばすのが難しい科目」なので、ちょっとずつでも練習です。
理系の仕事に就くと、「正確で読みやすい文章を、大量に早く書く能力」があるととても楽になりますから。^^
こどもにとって、ものづくりにとって大切なことは、結果よりも過程です。
完成までしばらくかかりますが、楽しみに見守ってください。(*^^*)
「失敗してはいけない」という空気が強くなったのは、いつ頃からでしょうか。
人のちょっとした失敗を見つけては批判する場面が増えたのも、その頃からかもしれません。
もちろん「昔の方が良かった」と言いたいわけではありません。
ただ、人が成長するには、失敗を受け止めてもらえる環境がとても大切だと思うのです。
こども技研は「失敗を経験できる場所」でありたいと考えています。
やがて子どもたちは、人の命を預かる、大きな責任を伴う仕事に就く日が来るかもしれません。
その時には、もう気軽に失敗はできません。
こども技研は前向きな失敗を歓迎します。
昔のように、失敗におおらかな環境で、「こうしたら失敗するんだ」という経験を積み重ねてほしいのです。
経験をたくさん積んで、自信を蓄えて、堂々と社会への扉を開けて進んでいってほしいと思います。
※教材費について・・今回は通常授業なので教材費はこども技研の負担です。特別なイベント以外は月謝以外に費用はいただいていません。
※今回はCuriosityクラスですが、ものづくり系の内容はDiscoveryでも行っています。