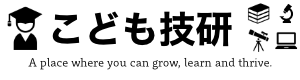ロボット制作の前回からの続きです。
いよいよ最終段階に入り、ぐっと難しくなってきました。
- 左手で押さえながら、右手でドライバーを回す
- 複数の差込をきれいにそろえて、蓋をする
- 電気の配線をする
- 図から組み立て方を読み取る
こんな、大人にとってはなんでもないような作業が、初めての子供には「とても大きな挑戦」になります。
それでも一生懸命がんばって、大人でないと難しいところ以外は、ほとんど自分で作ることができました。実際、95%くらいは自分ひとりで完成させています。

直接の製作だけでなく、部品をなくさない工夫や片付けの習慣も学びのひとつです。2回目の挑戦ということもあり、工具の使い方もずいぶんサマになってきました。
こちらも、様子がわかってきたので、子供が使うのに良いサイズの工具を揃え始めています。
完成後は一緒に動かして遊んだのですが、楽しすぎて写真を撮り忘れてしまいました…。
ロボットは「おうちの人に見てもらうため」に持ち帰ってもらったので、また次回ご紹介しますね。お楽しみに!
ものづくりを通して学んでほしいのは、技術そのものよりも次のような姿勢です。
- ひとりでやってみる、
- 失敗しても構わないことを知る、
- 失敗してもくじけない、
- できないときは助けを呼ぶ
- 最後ちゃんとできたら、途中の失敗はただの通過点!
- 自分でやると楽しい!
と言ったことです。これらは、生きていく上でさまざまなことに役に立つと考えています。
さらに、「自分がやってみたいこと」に自分で気がつくことで、自分に足りないことも見えてきます。
今回の製作だと、まだ小学2年生なので、説明書の漢字やアルファベットが読めません。ほかにも各種の規格、たとえばネジで3x15mmと書いてあっても意味がわかりません。
こうしたことに「もっと知りたい!!」と思ってもらうことが、こども技研の本質であり方針です。
小さな子供が、「模型の説明書を理解したいから、本を読んで漢字を覚えて、アルファベットを学びたい」と思う。
なんて、とっても素敵なことだと思いませんか? (*^^*)
※教材費について・・今回は通常授業なので教材費はこども技研の負担です。特別なイベント以外は月謝以外に費用はいただいていません。
※今回はCuriosityクラスですが、ものづくり系の内容はDiscoveryでも行っています。