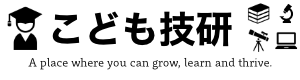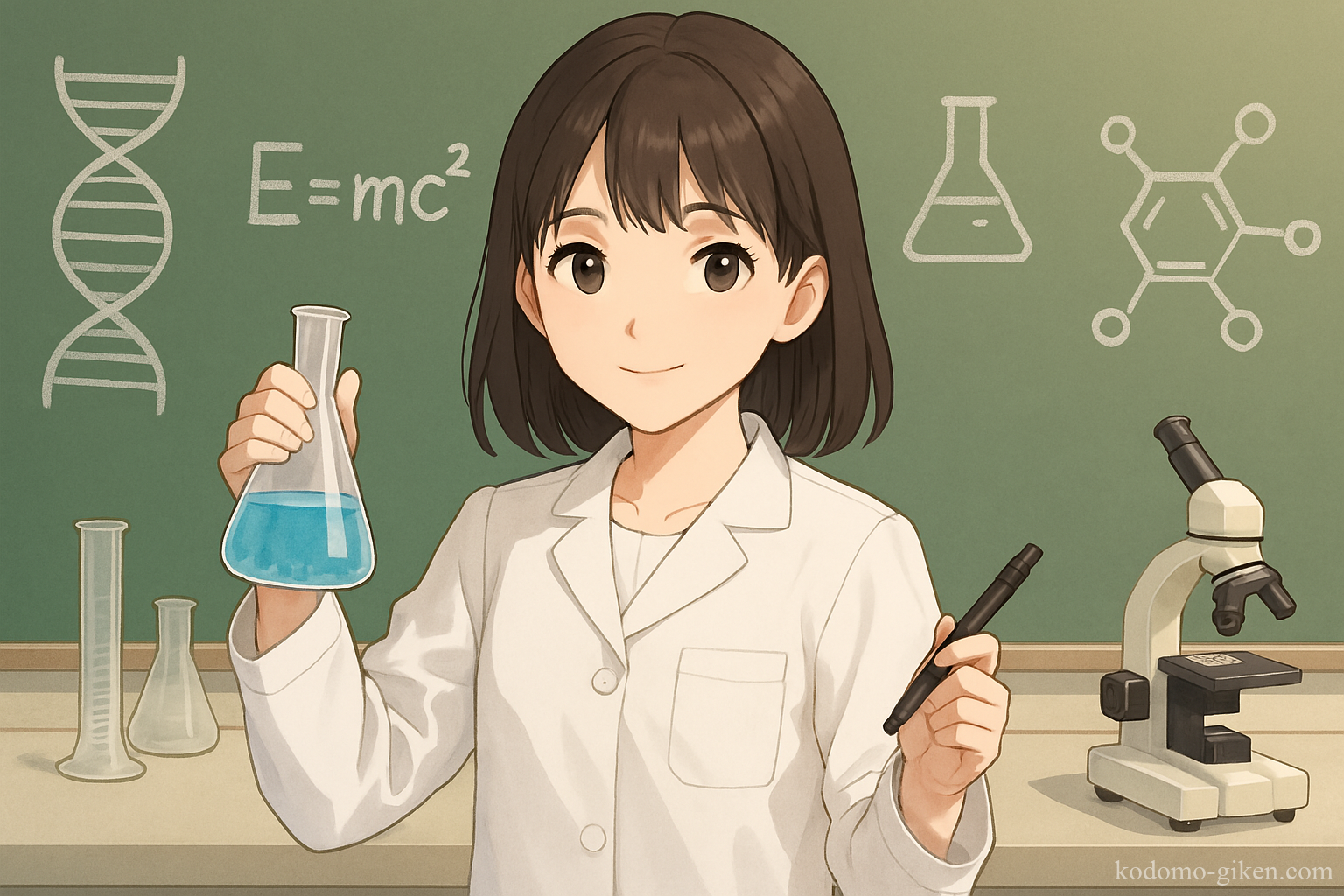小学校1年生と2年生には「理科」の授業はありません。
そのかわりにあるのが「生活科」という教科です。
生活科は知識を覚える授業ではなくて、見たり、触ったり、試したり、自分と身の回りのことを実感することが主な内容です。
今までで言う理科と社会科が一緒になったような教科です。生活科は「日本の子供たち全員が間違いなく通る科学の入口」でしょう。
虫を捕まえてみる。
石を拾って並べてみる。
草花を観察する。
町を探検する。
全部が立派な科学の入口です。
大人から見るとただの遊びに見えるかもしれないけれど、こういう体験の中に「不思議だな」「なんでこうなるのかな」が生まれるのではないでしょうか。
私は、子どもが石を拾っていたら好きなだけ拾ってほしいと思っています。
虫を見つけたら、怖がらずにじっくり観察してほしい。
花を見つけたら、愛でたり、匂いを嗅いだりしてほしい。
名前を覚えるのは、そのずっとあとでいい。
生活科の時間は、知識を覚える時間じゃなくて、こどもたちにとっては、見ていながら見えていなかった世界と出会う時間かもしれません。
自分の価値観で見ているだけでは気が付かなかったことを、学校で新しい視点を知り、ふれあい、いろんなことに気がつくようになる。素晴らしいことだと思います。
1年生と2年生は、その時間を思いっきり楽しんでほしいと思います。
子どもが「理科好き」になるかどうかは、知識よりも体験ではないかと思います。
虫取りも、石拾いも、道草も、全部が科学の入口です。
そう思うと、生活科だけじゃなくて、科学の入り口は日常にあふれています。
そうですよね。
科学は自然について考えて真理を探す学問ですから、「存在していること」にさえ気がつけば、いつでもそこで科学と触れ合うことができるのです。
世のお父様、お母様。
ご自身が自然が草や虫や石が苦手であっても、もしお子様が興味を持っていたら、危険ではない範囲でふれあいを見守ってあげていただけないでしょうか。
自然は時と場所によって移り変わり、2度と同じ姿を見せることはありません。
人は教育のために知育玩具などを作ります、そしてその効果はあると思います。(こども技研にもたくさんあります)
だけど知恵や思考の対象としては、千差万別の自然には敵いません。
人という生き物も自然の中で生きる生き物の一種である以上、自然に生かされているのですから当然だと思います。
こどもたちにとって、科学への入口が広くて、自由で、楽しいものであってほしい。
小さい頃の素直な目と心を持ったまま、大人の思考力や判断力を身につけていって欲しいと、私は思っています。