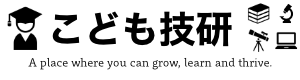ひとは、生きていく過程の分岐点で、いろいろな出会いがありますよね。
私は本が大好きで、本の神様がいると思っています。
本の神様は、本が好きな人をよく見ていて、その人の人生の中で、必要な本を必要なタイミングで、その人の手に触れるところに置いてくれるのです。
そんな出会いの中から、自然と科学のものから紹介します。
幼少期の私を自然科学好きに導いてくれた出会いの順に
学研の科学 学研
私が幼児の頃、母が「学研のおばちゃん」(学研の「科学」と「学習」を毎月各家庭に配達するパートさんのことをこう呼んでいました)でした。
折り目をつけたらあかんでと言われながら、せまい家の中で、そろーっと広げて写真を見た本が、私の理科への入り口でした。
母が学研のおばちゃんをやめた後も、そのまま私のために定期購読してくれました。
おもしろい読み物が、楽しい付録とともに毎月届くのは、当時の私にとって夢のようでした。
成績に直結することが求められる現在では、このような媒体はもうむずかしいのでしょうか。
私は学校は結果を競うものではなく、学び方を学ぶ場所だと考えています。
点数が支配する成績社会になり、こうした出版物が少なくなってしまったことがとても残念です。
理科の教科書 啓林館
小学校に入ってからは新しい理科の教科書を読むことがとても楽しみでした。
新年度の春に手に入れると、授業が始まるまでに家で完読していたと思います。
私の小学生時代の理科の教科書は啓林館でした。
啓林館さんの理科の教科書の写真を撮影させて頂くようになったことは深いご縁を感じます。
子供の科学 誠文堂新光社
夏休み、冬休みなどに、祖父のもとを訪れるといつも子供の科学がありました。
きっと私のために買ってくれていたのだと思います。
子供の科学は、どのページもわくわくすることでいっぱいでした。
読者投稿の発明コーナーなどもあり、自身でなにか作りたいなといっぱい感じさせてくれる雑誌でした。
大人になってからも技術書や電気系の趣味、そして図鑑など、誠文堂新光社さんはとても馴染みのある出版社です。一方的ですが。(笑)
これからも子どもたちの興味を掻き立てる本を出版してください。
ここにあげた「子供の科学」に加えて「National Geographic」と「Newton」は毎月定期購読しています。
研究員のこどもたちが読んでくれると嬉しいなあと思いながら。