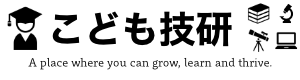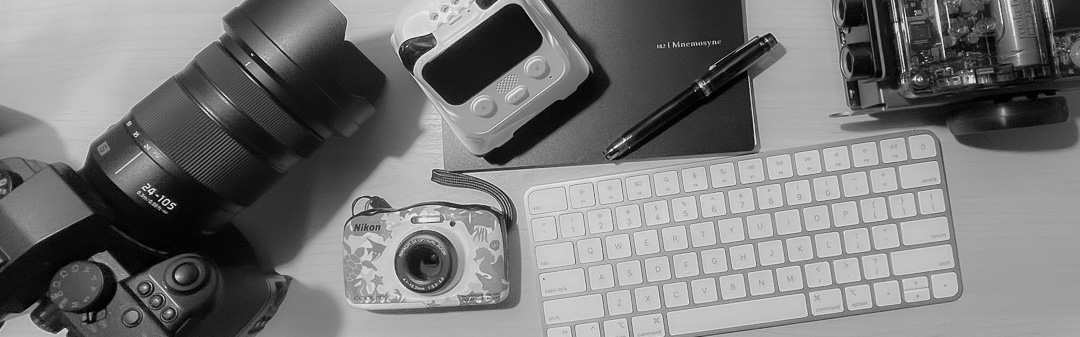
科学の始まりは、
好奇心と楽しむ心から
ITと科学を楽しむみんなの研究所
MISSION of こども技研
学びことの楽しさを知り、
学ぶことが好きな子供たちが育つ環境を作る
a place where you can grow, learn and slive.
こども技研でできること
こども技研のFirst Labは、虫や川や山、電車や飛行機や車といった『自然』や『科学』が好きな子どものための習いごとです。技術者・研究者を夢みる子どもを見守ります。
科学にふれあい、プログラミングを含むIT機器を使いこなして、学ぶことの楽しさを知り、観察する力、考える力、行動する力を養います。
こんなことをします
こども技研での学びは、大きくわけて、IT、STEM(理系総合)、学校教科、生活・心の学びになります。
この中で、STEMはこどもがやってみたいことを、その他はすべてを網羅するように進みます。
こども技研での学びは、学校や塾のようにみんな一緒じゃなくていいんです。こどもたちが自分のやりたいことを自分のペースで行います。
大人は、こどもたちに興味ややる気がでるようなことを見せたり伝えたり、必要な時にはサポートします。
学校の教科系の学び
言葉と数字は、最初に習得すべき大切な道具です。すべての学びはここからスタートします。
テストの点を取ることではなく、幼少期に身につけておく必要がある、将来のための基礎体力をつけることが目的です。
IT系の学び
IT機器は人に伝えるための道具、労力を省くための道具です。
楽しみながら長い期間をかけて、大人に負けないレベルのスキルを遊びながら学びます。
STEMの学び
理科と算数と国語の世界を、実際に体験して楽しみながら学びます。
見て、考えて、手を動かして、体験したものは、教えてもらっただけのものとは全く違います。
生活・心の学び
人は一人では生きられない、社会性の生物です。
こうしたことを経験すること、知ること、行動できる様になることは、実は世の中に出たら一番大切なことかもしれません。
まなびの概要

総合的な学びなので数値化するのは難しいのですが、おおよそこのような配分で学びます。
子どもたち一人ひとりに合わせるので、成長の度合いによって配分は変わります。
一般的なプログラミング教室・サイエンス教室との違い
思想が違います
- こども技研は、プログラム「も」作ります。サイエンス「も」学びます。
- それは子どもたちがそれらを知ることが目標ではないからです。
- こども技研でのプログラミングやサイエンスは、論理的な考え方、ミスを取り返す方法、わからないときにどうするか、人と協力し合うこと等を学ぶための手段です。
- 手伝ってもらって結果を出すのではなく、自分の力で過程を経験してもらうためのものです。
- この思想は、スタッフが本職のエンジニアだからです。児童・生徒という限られた期間の世界ではなく、社会にでてから本当に必要なことを身につけてほしいのです。
- テストの点数とか目の前の成績ではなく、こどもたちのずっと未来を見据えてサポートしたいと考えています。
- こども技研のこの考えは、すべてが、研究員のファイナルミッションのためです。
こども技研は、自分たちの力で観察する考察する作るところです
学校、塾、インターネットの世界など、現在の子どもたちはINPUTされる場所がいっぱいです。
だけど本当に実力になるのはOUTPUTの作業です。
こども技研は子どもたちに学び方を学ぶ場所を提供します。
たくさん失敗して、どうすれば失敗しないようになるのかを学んでほしいのです。
ものをつくるということは、『失敗を繰り返して過ちを取り除き、いいものに仕上げる』ということなのです。
こども技研の大人は、学校とは違い、教えるのではなく相談にのる立場です。手を引くのではなく、後ろから見守り、必要な時には横に寄り添い一緒に歩きます。
何らか職業のプロフェッショナルの方にはご理解頂けると思いますが、結局、自分の力で進むことが、実力をつけるための最短コースです。
だからこどもたちも、失敗の上に成功を見つけて、自分の力での達成感をあじわってほしいのです。
また、現代では、事務、開発、研究、創造、いろんな分野でITツールを使いこなすことが欠かせません。ITツールは『「使えるとすごい!」ではなく「使えて当然」の時代』です。
こども技研では、自分の手で書くという作業をしっかり学んだ後、観察すること、考察すること、まとめることなどに、使える場所には全てITツールを駆使します。
受動的な学習というINPUT作業で学んだ気になるのではなく、パソコンを中心としたITツールを道具として使いこなし、自分の成果をOUTPUTできるようになることが目標です。
社会に出ると答えがわからない問題を解かなければなりません。自分が出した答えが正解かどうかを自分で判断する必要があります。誰も正解を教えてくれません。
そのために必要なことは、たくさんOUTPUTして失敗することです。
失敗とは「失敗をしない方法を知るための経験」です。
たくさんの失敗から、成功への道を嗅ぎ取る力を身につけてほしいのです。
それから、諦めずに最後までやり切れば、途中の失敗は失敗でなくなり、ただの途中経過になるということを知ってほしいのです。
ここは、こどものためのこども技研です。子どもたちが自分たちで考える場所、自分たちで決断する場所、自分たちで行動する場所でありたいと思います。
学校ではできない失敗を、遠慮なくたくさんしてください。
こども技研がみんなに望むことは、目の前の成果ではなく未来へ続く成長です。
「先生の教え方が下手」と言うこどもや大人がいます。それはその人が学ぶことの楽しさを知らないからではないでしょうか。
本当に学ぶことが好きな人は『教えられるより自分で学ぶほうが楽しい!』ということを知っています。
また、世の中に出ると「誰も100%の正解を知らないことに最善を尽くす」ことが当たり前になります。その時に「誰もきちんと教えてくれない」なんて、何の言い訳になるのでしょうか。
学問とは教えてもらうものではなく自分から学ぶものです。
学問とは苦痛を伴いながら覚えることでなく、自ら観察し、推測し、試して、確かめることを楽しむものです。
こども技研は、学びを楽しむことを知ってもらうきっかけの場にしたいと考えています。
こども技研でのものづくり

いろんなものを自分の力で作ります。工作的なものを作ったり、観察したことから想像したりまとめたりします。
道端に綺麗な花が咲いていたら、ちょっと見てみます。写真を撮ってみます。パソコンに取り込んで拡大して見ます。新しい発見があったら、まとめてみます。子供たちが考えるミニ論文です。論文はpdfにしてもいいですし、ホームページにしてもいいでしょう。お父さんお母さんたちにも見て頂きたいのです。
こども技研では、こどもたちの感性でいろんなことに興味を持ってもらいたいと思います。
こうした行動の中で、観察し考えをまとめる力をつけると同時に、PCなどツールも使いこなせるようになってほしいと考えます。
大人に手伝ってもらってゴールしても、身につくことはまやかしの達成感のみです。
例えば、ロボットのプログラムを教材に書かれた通りにつくって動かせても、それがなにになるのでしょう。
作り方がわかっているものを作ることは技術ではなく作業です。しかも教えてもらって作るなら思考すらありません。
今の時代が必要としているのは、自分で作り方を見つけることができる人物です。
自分たちで「こうしたい」「どうすれば」と考えることが本当の力になります。
自分で決断して、自分で考えれば、例え結果が形にならなくても努力は必ず本人の実力になります。
それは「観察する」「思考する」「決断する」という訓練を、自らの意思で行ったからです。
「自分で」、この点をこども技研は大切にします。
これからの時代はゼロから創造できるということが大切な能力になります。
ゼロから物を作る能力を身につける道に、近道はありません。
こども技研の自然観察

上の写真は秋桜です。名前がわかるから、咲いていると注意が向きます。
では道端の雑草は?。
まったく気に留められていないと思います。
だけどそんな雑草にも名前があり、生命があります。
知っていることに気がつくことは、たやすいのです。ですが知らないことにはなかなか気が付きません。
知らないことに気がつくことはとても大切です。
そのためには「集中力」「好奇心」が必要です。
子どもたちには、自然を通じて「知らないことがいっぱいある」「楽しいことがいっぱいある」と感じてもらいたいのです。
ワクワクした気持ちでいることができれば、好奇心が芽生え、集中力が身につきます。
そして知識としての自然ではなく、体験するものの自然として接することができれば、読んだり聞いたりしただけの知識と経験したものの価値は全く違うことに気がつきます。
知識だけでわかった気になってはいけない、体験をして自分で確かめなくていけないと、心に深く刻んでほしいのです。
自然環境の中は、絶えず変化していく、こどもたちにとって理想の学び場です。
こども技研のFirst Labでは真っ白な気持ちで自然とふれあうことを大切にします。
自然観察が好きになると、ちょっとした自然の変化が楽しくなります。
そんなささやかなことも幸せなことと感じることができれば、きっと人生はより楽しくなります。
生きていると辛いこともたくさんありますが、道端の小さな花ひとつに心を惹かれている、その瞬間だけはその小さな幸せが自身の全ての世界でいられます。
実際はすぐに現実に引き戻されますが、その花や虫などの自然に、ちょっとずつ生きていく元気をもらえる気がします。
うまく言葉では言えないのですが、小さなことに幸せを感じられることは、人生を楽しく生きることにおいて大切なことのように感じます。
そしてその細やかなことに気がつく感性で、周りの人を大切にしてほしいと思います。
本を読むことの大切さ
本を読むことは、人生の潤いになります。
本を読むことは、学問の基本のひとつです。
言葉を正しく読むことができなければ、過去から蓄積されたものを学ぶことはできません。
言葉を正しく書くことができなければ、自分の考えを正しく伝えることができません。
文章を読むこと、書くことに労力が必要だと、その先になかなか進めません。
英語が苦手なひとが英語で思考することは難しいように、言葉は思考の道具なのです。
言葉・文章を手足のように自由に操ることができるようになるのが理想です。
言葉はなによりも最初に必要な道具です。
子どもたちはたくさんの文を読み、書いてほしいと思います。
ネットの時代になぜ本なのか?
インターネットの世界には、ブログやSNS、動画などに情報があふれています。
なのになぜ本なのかを書きます。
きちんとした書籍は、
- 筆者がその道の専門家です
- 文章の校正もプロが行っています
逆に言うと、ネットの情報は
- 素人が適当な情報を発信していることがある
- 文章がでたらめなことがある
のです。
ネットでは、素人が、他のサイトで書かれていることを、裏付けも取らずに真実のことのように、さも自分の知識のように話す・書くことが当たり前のようにあります。
こうした時、情報を調べている側が素人であれば、その情報の真偽を判断できません。
ひろゆきさんが言ったように「嘘を嘘と見抜けない人」はネットの情報に頼りすぎてはいけないと考えています。
また、ネットの文章は、ニュース記事であっても、素人が書いたような理解しづらいものが多くあります。
基礎が身についていく年齢だから、きちんとした文章、本物の文章にたくさん触れてほしい。
だから、きちんとした本に触れてほしいのです。
大切にしたいことを行うために
こども技研のスタッフがこどもたちのためにすることは環境づくりと見守ることです。
道は子供たちが自分で作らねば意味がありません。
道が見えていないようなら、その子に合った道の作り方のヒントを伝えます。
人が用意してくれた道を進んでも身につくことは少ないのです。
こどもたちが、
自分の力で、
成長し、学び、活躍できる場所
そのための環境を、
大人が、作り、見守る場所
A place where you can grow,
learn and thrive.
それがこども技研です