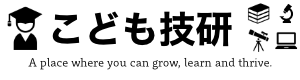こども技研では小学生の研究員に、一人一台の専用iPadを貸し出します。
こども技研に所属している間、そのiPadは各研究員専用のものになります。
原則、持って帰ることはできません。またこども用にかなり厳しい使用制限をかけています。
iPadの用途
iPadは様々な用途に使います。
一番最初、1年生から使うのは、保護者の方とのメッセージのやり取りです。
「こども技研についたよ」、「もうすぐ終わるから迎えに来てね」、「今から帰るからね」といった登所、退所を研究員自身が、自分のiPadで直接保護者の方へメッセージを送ります。最初は難しいと思いますのでサポートします。
次に使うのは、写真を撮ること、撮った写真を伝えたい人へ送ることです。
最初は、「今日はこんなことをしたよ!」と保護者の方への日報(?)を。(^^)
写真や動画を手軽に撮れることはとても便利です。自然観察中や実験の間でも撮ってもらいます。
そのために頑丈なケースに入れて、ストラップでさげるようにしています。
撮った写真は慣れてきたらホームページへも研究員自身で載せるようになるでしょう。
「見つける」、「調べる」、「考える」に加えて「伝える」も大切な要素だと考えています。
それから、各種学習アプリを使うことです。
今までの経験上、百ます計算なども、プリントよりもタブレットを使う方がずっと夢中になって取り組む場合が多いです。
算数・国語・英語など、学校の勉強も集中力が続く範囲で取り組みます。嫌になる程はしません。気持ちが前向きでない時にしても身につきませんから。
一番時間を使うのはプログラミングでしょう。
トップの写真はScratchというツールでのプログラミングの画面です。こども技研でのプログラミングに対する考え方は「集中力や注意力を養うためのツール」です。プログラミングそのものは、わざわざ学ぶほどのものでなく、論理的な思考力がつけば自然にできるようになります。
経験上、スポーツで言うと、テクニックよりも基礎的な運動能力こそが必要だと感じています。テクニックは現場で磨くことができますが、思考力・注意力が弱ければ、いくら学んでも業務レベルのシステムを作ることは難しいです。
なぜ各自の専用iPadにするのでしょう?
一言で言うと、「前の続きを簡単にできるから」、「他の人が見れないようにしたいから」です。
iPadのアプリは、作業途中を覚えているものが多いので、休みを挟んでも継続して続けることができます。
だけどもし共有なら、他の人の作業の続きになってしまうので、テンションがさがってしまいます・・・百マス計算のタイムトライアルとか、他の人に更新されたらつまらないですよね・・・
それからもうひとつ、こちらもとても大切なことです。
「モノを大切に使って欲しい」のです。
iPadは研究員である限りはずっと自分のものです。だけど、いつか卒業したら、そのiPadは他の研究員に引き継がれていきます。
「大切に、だけどガンガンつかう。自分のために。次に使う人のために」です。
iPhone等を使っておられる方はご存知だと思いますが、iosはappleIDという概念があります。appleIDは各自が取得して、アプリの購入等はこのIDを使って行います。
こども技研のこども部門では、各自のiPadのappleIDは入所時に取得して、以後こちらで管理します。研究員の進度にあわせて必要があればこちらでそのappleIDでアプリを購入します。(代金はこども技研が負担します)
お子様がこども技研を卒業する時、今まで使ってきたappleIDをPWと一緒にお渡しします。これから研究員がもつiPhoneやiPadにそのまま使えるので役に立ててください。
どんなiPadを使うの?
最新のものではなく、用途に耐える範囲での中古品を使います。
こども技研は大人が仕事で使うレベルの機材を揃えていますが、大人も「用途以上の機材」はそうそう用意してもらえません。(笑)
使える範囲での節約は、月謝を必要以上にあげないためでもあります。
ご理解ご協力をお願いします。
期待していること
とまあ、もうすぐ還暦を迎えるオジサンはこのように思っていますが、実際にこどもに渡すと、もっといろんな発見があるでしょう。笑
どんなことに使ってくれるのでしょうか?
のびのびと、自然や科学を楽しんで欲しいなあ。
未来はこどもたちが変えていく。
このことがいちばんの願いです。

memo
こども技研では、小学生の研究員が自分のスマホ、タブレットを所有することを禁止しています。
「所有していると入所できない」、「途中で所有したら即退所」というとても厳しい制限です。
入所条件・ルール・マナーでも少しふれていますが、悪意ある大人とも同じ世界へ繋がるインターネットの世界は、こどもにとってとても危険です。今の大人が昔言われた、「テレビを見すぎてはいけない」といったレベルの危険ではないと考えています。このことに関してはまた機会を詳しく設けて述べます。
ネットとの付き合い方を学ぶことも、iPadに使用制限をかけて大人の目の前だけで使ってもらうことの狙いです。