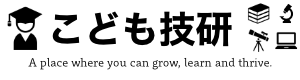先日、慶應義塾の伊藤公平塾長が「国立大学の授業料を現在の3倍、150万円にすべきとの意見」を出しました。これはあくまでも「質の高い教育をするための費用をまかなうために」ということらしいです。
「大学で質の高い学問を行いためにはお金が必要なこと」はよくわかります。
しかしながら、裕福な家庭に育った方には150万円というのは大した金額ではないのかもしれませんが、私の家庭では当時の30万円という学費でも負担でした。150万円という金額は「教育の質を担保する」以前に「お金のない家庭からは大学生になれない」という状況を生み出します。
そもそも国立大学にお金がないのは「2004年の国立大学法人化」で「お金を出さないのに政府による支配を強化された」(独立と言いながら国によりコントロールされる)からです。
今は我が子が国立大学に通っていますが、学生たちは、都会の私立大学の学生に比べるととても質素な生活をしています。
こどもたちは生まれる家庭を選べません。
あまり裕福ではない家庭に生まれながらも、学問への情熱を持ち、優秀なこどもはたくさんいます。その子たちの受け皿が公立の大学だと思います。恵まれた人の視点で、すべての学生の立場を判断してほしくはありません。
私も国立大学出身ですが、学生の頃、先生たちからよく「君たちはみなさんの税金で学んでいるんだ。しっかり学んで社会へ還元しなさい」と言われたものです。
こどもたちは社会全体のたからものです。
家庭の財政状況にかかわらずに大学で教育を受けることはできないのかというシンプルな疑問から「全ての国立大学の学生&院生の授業料・入学料をゼロにするには、どのくらいの予算が必要なのか」をchatpgtに投げてみました。
その結果が以下です。
ChatGPTからのコピーです
日本の 国立大学を全て無償化 するために必要な予算を概算すると、以下の要素が関係します。
1. 国立大学の学生数
• 文部科学省の統計によると、日本の 国立大学の学生数は約60万人(学部生)。
• 大学院生を含めると、約80万人。
2. 授業料の平均
• 国立大学の年間授業料 は 53万5800円(標準額)。
• その他の 入学金 や 施設設備費 を考慮すると、年間平均で 約60万円 の学費負担と見積もる。
3. 必要な年間予算
• 学部生のみ無償化 → 60万人 × 60万円 = 3600億円
• 大学院生も含めて無償化 → 80万人 × 60万円 = 4800億円
4. 既存の奨学金・補助金との比較
• 日本では給付型奨学金や授業料減免制度がすでに一部実施されているが、完全無償化とは異なる。
• 例えば、「高等教育の修学支援制度」にかかる予算は年間 4000億円 程度(私立含む)。
• そのため、完全無償化には 追加で2000〜4000億円程度 の財源が必要と見込まれる。
結論
• 国立大学の学部のみ無償化 → 約3600億円/年
• 国立大学の学部+大学院無償化 → 約4800億円/年
これは日本の国家予算(約110兆円)の 約0.3〜0.4% に相当する規模である。
念の為に文科省のHPから学生数等のウラは人力で取りました。資料「令和6年度学校基本調査(確定値)について公表します。」
通学にかかる費用は我が子のものから相応であることがわかります。
最後のセンテンスが結論です。
国立大学の学部+大学院の無償化に必要な予算は約4,800億円/年
もうひとつあげておきます。
こども家庭庁の令和7年度予算案は約7.2兆円
(一般会計約4.2兆円、特別会計約3兆円の合計)
こども家庭庁の予算のたった6.6%で、すべての国立大学の学生と大学院生の授業料を無償化できるのです。
各県にひとつずつ、無償で学べる大学があるなら、どれほどの学生が勉学に励むでしょうか。
こども家庭庁の予算は、それほどに大きいものです。
官僚と政治家にきちんと政治をしてもらう(「政治をさせる」と言いたい)のは、これからの子どもたちのための、今の大人の義務だと思います。
memo
公立高校は「高等学校等就学支援金制度」を通じて、公立高校の授業料を原則無償化されていますが、実際に公立高校へ通わせると、「授業料以外の費用(教材費、制服代など)」で年間に平均10〜20万円程度かかります。これらまで無償化するための予算を試算すると年間約5兆円(現在の授業料無償化分4000億円+追加4.6兆円)でした。
つまり、現在のこども家庭庁の予算で「公立高校のほぼ完全な無償化」と「国立大学&大学院の授業料&入学金の無償化」を行うことができるのです。
memo
こども家庭庁の予算は障がいのある子どもたちの補助なども含まれています。
これらは生きるために必ず必要なことであり、教育よりさらにもっと生命に近い、根源的で基本的人権にかかわることだと考えます。
そのため、こども家庭庁ではなく、老人の介護等と同様に、厚生労働省でもっと根本的に取り組むものではないかと考えます。