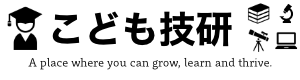挨拶 – 学ぶことへの思い
初めまして。
こども技研の所長、FINDERです。
この「こども技研」は、私が会社員のシステムエンジニアとして働いている頃に「子供の頃からこんなことができたらなあ」と、夢を見ていたものを形にしたものです。
私は会社を退職した後、フリーランスのエンジニア兼カメラマンとして独立しました。
フリーになってから、取引先各社の状況、若い人たちの成長を見ていると、ますます「こども技研」の必要性を感じ、形が具体的になってきました。
名前は当時は考えていなかったのですが、創設する数年前に「こども技研」と名付けました。
名前だけ見ると“子ども向け?”と思われるかもしれませんが、じつは子どもも大人も対象です。
子どもみたいな好奇心と素直な目で、ものごとを見て、楽しめる場所にしたい——そんな願いを込めています。
私自身を振り返ると、多くのことが「おもしろそう!」で始まっていたと思います。
幼少の頃、三輪車を買ってもらっても、乗ることよりもひっくり返してタイヤを回していた私は、中学生3年生の夏に加古川の星電社に入り浸って店頭のマイコン(パソコンのことを当時はそう呼んでいました)で、プログラムを書いているような少年になりました。(店員さんが「宣伝になるからやってやって」と言ってくださってました。良い時代でした)
その後、「コンピューターのことをやりたい!」と思って、明石高専の電気工学科に進みましたが、学校ですることは机上の学問が多く、少しものたりませんでした。
そのため、その頃に最も興味を持っていた海洋学を学ぶために一から大学へ入り直しました。
大学へ入って思ったことは、「やりたいことを学ぶってめちゃくちゃ面白い!」ということです。
ある意味、社会人が学び直しで大学へ入ったのと同じようなケースだったのだと思います。
卒業後は環境関係の企業に入社しましたが、会社選びに失敗して、結局そのあと続けた仕事は電気系のエンジニアでした。
半ば仕方なく戻った電気関係ですが、仕事としてやってみると、おもしろいのなんのって!!
あれほど、面白くなかった理論とかが、「ああ、きちんとやってればよかったー!」と、急に実務に結びつくのです。
必要に迫られての学び直しの楽しいこと!!笑
この時に、私には机上の学問から入るより、実務から入って必要になれば学ぶスタイルがあっているとわかりました。
そうして数年が過ぎて、後輩たちの面倒を見る頃になると、そのスタイルがあっているのは私だけじゃないことがよくわかりました。
ほとんどの子たちは、あれこれ説明するより、まずやってもらって、実際に困ってから手を差し伸べた方が、確実に身につくのです。
私がこのスタイルを取ったのは、先輩や上司がそうしてくれたからです。
「とりあえずやってもらって、失敗しそうなところは気にかけておく。もし失敗したら、責任は取る」——そんな姿勢を見せてくれる人たちでした。
私は、なんと恵まれていたのでしょう。
そんな上司や先輩たちに感謝の言葉を伝えると、いつも言われたことがあります。
「わしに礼はいらんから、また若い衆にそうしてやってくれ」
こども技研をつくるいちばんの想いは、ここにあります。
私はもうエンジニアとしては、片足を棺桶に突っ込んでいます。だけど、まだ少しでも現役で通用するうちに、若い子たちに伝えたい。
学校の “緊張感も責任もないゆるい環境” ではなく、本当の現場に近いスタンスで、おもしろさとしんどさと、その向こうにある達成感を伝えたい。
こうした今までの社会人としての経験から、こども技研では、「好きなことを自分でやってみる」ことを大切にしています。
自分が好きなことを自主的に学ぶことはとても楽しいことです。
自主的に学ぶことは、やらされることよりも、ずっと実り多いものです。
ひとつのことを、自分の意思でしっかり学ぶことができれば、他のことの学び方や楽しみ方もわかってくるのです。
体を動かすことが好きな子がスポーツを習うように、
音楽が好きな子が楽器を習うように、
乗りものや機械、花や虫など、理科系のことが好きな子どものために、学問を楽しむきっかけになる場所として、こども技研を創りました。
ひとりでも学ぶための方法と、学ぶことの楽しさを知ることは、目の前の成績のためだけでなく、その人の人生の幸せにつながると信じています。
それは年齢に関わりません。
いつだって、思い立った時がいちばん若い自分です。
やってみたいことをやってみましょう。
これが、こども技研創立の強い思いです。
所長 : FINDER