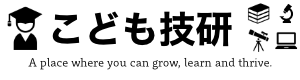「目で見えている、なめらかな“光の世界”が、どうやって“データ”になってるの?」
そんなことを思ったことはありませんか?
普通の写真教室ではしないと思いますが、ここは「自分でやってみるモノづくりの教室【こども技研】」です。
「なぜ?」を解決しないで、「とりあえずそう覚えといて」は、あまりやりたくないのです。😅
今回は写真でのアナログとデジタルの関係をみていきましょう。
では本編です。
昔のカメラはフィルム、今のカメラはデジタル。昔の音楽はレコード、今はスマホで聞くのが当たり前です。
デジタルって便利だけど、「どうやって“数字”になってるのか?」をちゃんと知ってる人は少ないかもしれません。
🌞 光の世界はアナログです
光の明るさや色は「なめらかに変化する」ものですよね。
- 太陽がのぼると、すこしずつ明るくなります
- 青い空も、場所によって少しずつ色がちがいます
この「なめらかに変わる」ことがアナログです。
📸 カメラはそれを“数字”で記録する
カメラのセンサーは、レンズを通して入ってきた光の強さに応じて、電気信号として発生させます
でもその電気の流れは、それをそのままでは保存できないので、数値に変換します。
この作業を「アナログからデジタルへの変換」(AD変換)といいます。
🔢 bit(ビット)ってなに?
ここで、デジタルでどのように数字をあらわすかを考えます。
アナログは、「ずーっと続いているデータ」ですが、デジタルは「0か1」かの世界です。
この「0か1」は「スイッチがONかOFFか」と同じ意味です。
デジタルでは、このようなスイッチを、とてもたくさんつかって、数を表します。
このスイッチ一つを「1ビット」と言います。0か1か、オンかオフか。これっていわゆる二進法ですよね。
一旦これはここで置いておきます。
まとめると、アナログデータをデジタルデータに変換するとき、「ずーっとつながっているアナログのデータを、どのくらい細かく区切るか?」を表す最小の単位が**bit(ビット)**です。
🖼 たとえば空のグラデーション
たとえば、青い空(ここでは完全な”青”ということにします)という色を1ビットで表すと、「0:黒」、「1:青」の2種類しかありません。途中の色々ある青い色は全部省略されてしまいます。
これが8ビットだと00000000から11111111まであらわすことができます。これは十進数にすると0〜255です。つまり、真っ黒から青までを0を含めると256段階の階調であらわすことができるようになります。
ちょっと実際に見てみましょう。
webではcssというものを使って簡単に色をデジタルで表すことができます。
光の3原色、RGBのそれぞれ00000000、01111011、11111111です。
| 色 | 00000000 | 01111011 | 11111111 |
|---|---|---|---|
| R(赤) | |||
| G(緑) | |||
| B(青) | |||
| RGBすべて |
光の世界では色をRGBの3つで表すことができます。
つまり1色あたり256色を表現できるということは、3色使えば256 x 256 x 256 = 約167000色 表現できるということです。
さらに、この数値は8bitですが、12bitの場合は、4096 x 4096 x 4096 = 約687億色となります。
つまり、bit数が多いほど「細かくて」記録できるのです。
📘 まとめ
カメラが見ている世界は、なめらかに変化する“光の世界”。
それを写真として記録するために、数字に変換する=デジタル化というしくみが使われています。
デジタルの世界は「0」と「1」の組み合わせです。
その組み合わせの数が多いほど、明るさや色を細かく段階的に記録できます。
この細かく分けた一つがbit(ビット)です。
1ビットはスイッチのようなもので、オンかオフ、0か1
これが8個あると8bitと言います。
そして、8bitなら256段階、12bitなら4096段階。bit数が増えると、よりなめらかに、より自然な階調のある写真を作ることができます。
このしくみを知っておくと、
- RAWとJPEGの違い
- ISO感度でノイズが出る理由
- カラープロファイルの意味 など、
いろんな「なぜ?」がつながって、写真の世界がもっと深く見えてきます。
「見えているものが、どうやって“写真”になるのか?」
そんな疑問にふれるのも、こども技研の“実験”のひとつです📷✨