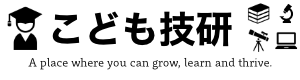生徒ではなく研究員と呼ぶ理由
こども技研では、すべての子を「研究員」と呼びます。
探究や制作に取り組む子たちはもちろん、英語や数学の教室に通う子も同じように、「受け身で教わる生徒」ではなく、自分から学ぼうとする姿勢を育てることを大切にしているからです。
たとえ授業形式であっても、目的意識を持って学びに向き合うその姿は、私たちにとって立派な研究員です。
こどもたちを研究員として扱う理由
こどもたちが研究員であるのは、自分の意思で未来へ進んでほしいから。
人に言われた眼の前のことをこなすだけでなく、自分の行きたいずっと先の未来を見て進んでほしいから。
学校の勉強は、目の前のことをこなしていくスタイルです。
児童、生徒である子どもたちは、学校が決めた、集団のためのスケジュールに則って、目の前のことをこなすことを強いられます。
だけど、それって面白くない。
少なくとも、こどもの頃の私は楽しくありませんでした。
つまらないのではないんです。
学校で習っていることはとても興味深いこと、楽しいことばかりでした。
もっと先へ進みたいなあ、もっとゆっくり深く知りたいなあ、と言った気持ちです。
この気持ちを大切に育てるために、こども技研では、こどもたち研究員一人ひとりが、自分なりの目標や進み方を考える姿勢を大切にしています。(もちろん必要があれば、大人が一緒に整理したり、ゴールを提案することもあります)
「やらされる」ではなく、「じぶんで決める」、「納得して取り組む」ことが、力につながる。
そんな実感を積み重ねて、自分の意志で動ける人に育ってほしいと思っています。
そのために、こども技研では「こどもたちは生徒・児童ではなく”研究員”」です。
研究員成長のための基本方針
いわゆる塾とは全く違います
例えば、ちょっとだけ考えただけで問題集の解き方と解答を見て、難しい問題があっさり解決したとします。
でもそれは──
まやかしの達成感が身につくだけです。
その壁は、ハシゴをかけてもらって超えたのです。
自分では、壁を越えていないのです。
すると、実力はついていないのに「ついた気になる」。
そして、「教えてもらう」ことに慣れてしまうと、
自分で考えることをやめてしまいます。
やがて、自分ですることをやめた人は、他の人に依存するようになります。
そして、何かうまくいかない時、「他の人のせいだ」と思うようになります。
けれど本当は──
自分で他人なんて変えられない。
誰かのせいにしているうちは、その人の成長は止まってしまいます。
社会に出れば、「答えがわからないこと」を解決する場面にたくさん出会います。
そして、その答えは誰も教えてくれません。
こども技研が、安易に解決方法を教えないのは、
「答えのない問いに、自分なりの答えを見つけられるひと」になってほしいからです。
だから教えず、一緒に考えます。
答えが出たら、一緒に喜びます。
素敵な答えだったら、一緒に感動します。
こどもたちに必要なのは、こどもたちの気持ちへの共感です。
そして、大人の役目とは──
「自分の力で、自分の道を進むことの大切さと方法を伝えること」だと、こども技研は考えています。
研究員としての成長
こども技研では直接的な教科の先取りには慎重ですが、先に学ぶことはたくさん経験します。
それは「ずっと先に目標を置いているから、知らなきゃならないことがたくさんある」からです。
例えば、みんなでモノを作る時、「この部品が何個必要かな?一人何個ずつ作ったらいいかな?」というケースがあったとします。
このようなことが年長さんや小学1、2年生でミッションの遂行に必要になると、将来学ぶ割り算や掛け算の先取りになります。丸暗記で九九を覚えるより、必要になって覚える方が断然楽しく身につきます。
難しそうに思いますよね。
だけど好奇心の強いこどもは小学生であっても「やってみたい」と思います。そんな子はたくさんいます。
その機会を与えられていないだけです。
今はまだ知識が足りなくて難しいから理解できなくていいんです。
興味を持つ心、チャレンジしたい気持ちそのものが素晴らしいことです。
「自分も大きくなったらできるんだ!できるようになりたい!」そんな気持ちが芽生えることを大切にしたいのです。
学校の授業の予習をするように、座学としての予習をすると、後から受ける学校の授業が「もうやったからつまんない」になります。
だけどもっと先に目標を持った実験や研究の中での先取りをした後での授業は、「あ!あのことだったんだ!」と前向きな気持ちで取り組みやすくなります。
生活に密接している科学は、そのまま実践で先取りします。
こども技研で興味を先取りして、学校でしっかり学ぶ。
ずっとずっと先を見て、
ワクワクしながら
楽しく進む。
自然と力がついている。
それがこども技研の研究員のスタイルです。